私の野菜と果物の記事を読んだ友人から、こんな質問をもらいました。
野菜&果物回に関して質問です!野菜と果物は合計400グラム摂るとよいとありますが、野菜と果物の比率は気にしなくてもよいでしょうか。果物が高いので、果物でなければならない理由がなければ、野菜で代替したい人は多いのではないかと思います。
面白いテーマだったので、記事にしてみようと思います。野菜と果物の記事に関しては下記の2つです、まだの方はこちらからどうぞ。


結論
比率で管理する必要はないと思います。普段から目標にしやすい考え方として、下記をおすすめします。
- 野菜と果物は合わせて400g以上を目標にする。
- 果物を200g程度、すなわちりんごMサイズの3/4個程度を目標に摂る。
- 1.で摂取した果物だけでは400gに足りないはずなので、そのぶんをしっかり野菜で摂る。毎日3~5皿が目安。
なぜそのような結論に至るのか、説明してまいります。
栄養の絶対的な正解は未だ不明である 最も確からしい範囲を目指せ

- 私が1日に摂取するべき野菜は何gですか?
-
知らなーい。
なんて不誠実なんだ! と思われるかもしれませんが、コレは本気で言っています。わからんのですよ!
そもそも論として栄養の研究というのは、疫学研究がメインです。疫学というのは聞き慣れない言葉ですよね、辞書を引いてみましょう。
えき‐がく【疫学】
読み方:えきがく人間集団を対象として、病気の原因や本態を究明する医学の一分野。感染症の原因や動向を調べる学問であったが、今日では、公害など広く健康を損ねる原因などを研究対象とする。
デジタル大辞泉より
要は、どういう食習慣をしている人が、病気になりやすい(またはなりにくい)のかを調べているのです。「栄養素◯◯を摂取すると、△△が生成されるので、□□g摂取した方が良い」みたいに、はっきりと必要な栄養素量が求められるわけではないんですね。
そうした研究から求められるのは(何か効いているのかはよくわからんが)コレをコレ位食べている人たちが、そうでない人より◯%くらい病気になりにくいようだよ、というなんともパッとしない結論です。人類にとっての真の必要量がわかっている栄養素はほぼないんです。
しかし、なにもわからなくても我々は今日も明日も栄養を摂らなければなりません。なので、せめて今わかっている研究結果のうち、精度が高そうなものを選び取り「わからないけど少なくともこの範囲は安全だ」「多分だけどこれ以上はやめといたほうがよさそう」を積み重ねて行くしかないんです。
栄養学という科学は『確からしい範囲』を積み上げる営みなのです。
野菜と果物の摂取量について
ご多分に漏れず今回のご質問内容である「理想の野菜果物比」も、結論はわかっていません。そのため、最も間違いがなさそうな範囲をおすすめしたいところです。
参考にすべき研究結果をまとめてみる
今回は3つの研究を参考にしていきます。
- 1.野菜や果物をたくさん食べると健康に良いのかを調べた研究
-
- 果物・野菜の摂取量が多いほど死亡率は低下。
- リスク低下は1日5サービング(400g)程度で最大となる。
- 6サービング以上では追加の効果はほとんどなし。害もなし。
- 2.果物と野菜の摂取と2型糖尿病のリスクについて調べた研究
-
- 果物は適量摂取すると2型糖尿病のリスクを下げる。
- 効果は2~3サービング(160g~240g)で最大となる。
- 果物の摂取量が3サービング(240g)を超えると少しずつリスクを下げる効果が弱まる。
- 果物の摂取量が4~5サービング(320~400g)摂取すると少しずつリスクが上がるようだが、もともとそんなに果物たくさん食べる人は少ないのでよくわからない。
- 3.果物と野菜の摂取と死亡率を調べた研究
-
- 果物・野菜の摂取量が増えるほど死亡率は低下する。
- 効果は 果物2サービング(約160 g)と野菜3サービング(約240 g)で最大となる。
- 果物と野菜の比率が変わると結論が変わるか否かは書かれていない。
- 6サービング以上ではリスク低下のカーブは 頭打ち。
わあ、ブログの書き方書籍では絶対にやるなと言われていた、小難しい文章の壁ができてしまいました。
でも大丈夫、これをどう読んでどうすべきか考えるのは私めにお任せください!
果物と野菜の黄金比はなさそう
質問者さんは野菜と果物の比率について知りたがっていましたが、ここは気にしなくて良いと判断します。
「死亡率を下げる効果は 果物2サービング(約160 g)と野菜3サービング(約240 g)で最大となる」という結論があるので「じゃあ果物2:野菜3がいいじゃん」と思うかもしれませんが、私はそうは思いません。
よくよく研究内容を読んでみたのですが、逆(果物が3で野菜が2)だったら死亡率が下がらないというわけでも無さそうですから。
さらに極端な思考実験ですが、上記の食べ方をしている人に、追加的に大根Lサイズ半分(500g)食べてもらっても害はないはずなんですよ。
そう考えると、果物と野菜の比率に大した意味はなさそうと判断できると思います。
不足も過剰も気をつけなきゃならない果物の目標から決めよう

比率は気にしなくて良いと判断しました。では絶対値で正解が定められそうな目標はあるでしょうか。
果物には、野菜と独立して適正な量を食べると糖尿病のリスクを下げる効果があることがわかっています。
「果物が糖尿病リスクを下げる効果は2~3サービング(160g~240g)で最大となる」「果物の摂取量が4~5サービング(320~400g)摂取すると少しずつリスクが上がる」ということは、果物には正解のg数がありそうです。
研究からは特定のg数が真の正解だとは導き出せませんが、そこからなるべく近そうなところを目指すべきです。
こういう時に、追加で必要なのが「普段どのくらい果物を摂っているか」という情報です。
一般的な20歳以上の日本人は、令和5年国民健康栄養調査の結果を見ると、20歳以上の日本人は果物は93g程度摂取しています。目指すべき量より摂取量が少ないのは間違いなさそうです。
更に、質問を受けた友人とは何度も一緒に食事をした事があるので、思い出してみます。一般的な日本人と比較して、彼は果物を多く食べていたかな……? いや、食ってねえな。バイキングでは結構茶色い食事してた気がする。
というわけで不足がほぼ確実である果物をまずたべなさい、と発信するのが実際的だと思いました。
「果物が糖尿病リスクを下げる効果は2~3サービング(160g~240g)で最大となる」とありますから、その中央値である200gを示しておくのが覚えやすく、もっとも無難でしょう。200gとなる果物の量は下記のとおりです。
- りんごMサイズ 3/4個
- みかんMサイズ 2個
- バナナLサイズ 2本
まずはこの量を目指してもらいましょう。
400gという大目標を達成するために足りない分を野菜で補う 目標は3~5皿以上
野菜と果物の効果は「果物・野菜の摂取量が多いほど死亡率は低下」「リスク低下は1日5サービング(400g)程度で最大となる。」となっていますので、目標量の果物を食べたうえで、400gまでのギャップを野菜で埋めるのが良いでしょう。
ここでポイントなのが「6サービング以上では追加の効果はほとんどなし。害もなし」という結論もあることです。果物は過剰摂取によるデメリットはありそうですが、果物と野菜の合計量が増えても実害は無さそう、じゃあ野菜を食べ過ぎるデメリットはほぼないと判断して良いと思います。
果物と違い、野菜は複数の種類を食べることが多いです。生の果物を食べる場合1日に1~2種類程度でしょうが、野菜はもっと多くの種類を食べるのが普通です。
種類が多いと、重さを把握するのも困難になります。何十種類もの野菜を毎日量るのは現実的ではありません。
そこで、野菜料理の皿数を1日に3~5皿とすることを目標として提案します。
今回紹介した研究では、1皿は80gが目安とされていますので、『おいしい健康』レシピページよりちょうど80gくらいの野菜炒めの画像を引用します。
出典:『おいしい健康』レシピページ (最終アクセス:2025年9月29日)
サラダでもいいですね。市販品のパックサラダでもちょうど80gのものがありました。
出典:セブンプレミアム公式サイト 商品詳細ページ(最終アクセス:2025年9月29日)」
これくらいの野菜を3~5皿食べていただければよいでしょう。おひたしや付け合せのような少なめの野菜料理は、2品で1皿分という計算の仕方が現実的でしょう。
果物を200g食べられているのであれば3皿(240g)でいいし、果物が少ししか食べられなかった日は5皿(400g)を食べれば(果物のメリットは得られないものの)野菜の健康効果は得られます。
あらためての結論
- 野菜と果物は合わせて400g以上を目標にする。
- 果物を200g程度、すなわちりんごMサイズの3/4個程度を目標に摂る。
- 1.で摂取した果物だけでは400gに足りないはずなので、そのぶんをしっかり野菜で摂る。毎日3~5皿が目安。
というわけで、冒頭の結論をもう一度お示ししますが、わかっている情報でパズルをするとこんな目標が現実的じゃないかと判断いたしました。参考になれば幸いです。






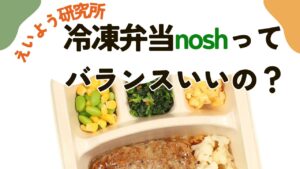





コメント