食塩に含まれるナトリウムは、摂りすぎると高血圧を引き起こすことでよく知られています。ただ、「有名な健康情報」ほど世の中にあふれてしまい、何が正しいのか判断しづらくなることもあります。たとえば「味噌は体にいい」「カリウムは高血圧を防ぐ」と耳にすることも多いですが、それは本当なのでしょうか? 今日はナトリウムに関する情報を解説していきます。
結論
- 何に入っているナトリウムでも過剰摂取のリスクはある
- 干物や塩蔵魚卵など塩辛い食事に含まれる食塩は胃がんの原因にもなる
- 酢、からし、代替塩を使うのは減塩に効果がある
- カリウムを適量摂取すると高血圧を予防する効果がある
どの食品に入っているかによってナトリウムの影響は変わるのか?
味噌推し情報はけっこうある

「味噌 食塩」で検索してみてください。どうでしょう、なんか味噌は健康に良いから摂ってもいいみたいですよね。味噌は放射線を防ぐ、というキャッチーな題目の記事さえあります。
実際のところ、特定の食品が病気に良いのではないかという研究は数多く存在します。
古くから、人類は体によい食品や薬などを追い求めてきました。今後も「これは体にいいのではないか?」という検討は続いていくことでしょう。
でも味噌推し情報よりもナトリウムに関係する論文のほうが圧倒的に多く質が良い
しかし、それ以上にナトリウムの過剰摂取に関する根拠ある論文は多いです。
日本において、最も妥当性・信頼性が高い栄養のガイドラインは食事摂取基準です。2025年度版の食事摂取基準において、ナトリウムの過剰摂取に関する記述は充実しており、42篇もの文献や研究を参考にして検討されています。少なくとも味噌単体を扱う論文よりナトリウムを扱う論文のほうが多いです。
そして、ナトリウムを扱う論文で過剰摂取を是としている論文は、ほぼ皆無です。
 ヨシ
ヨシ味噌は一部地域でしか食べられていませんが、ナトリウムは世界中でたべられていますし、当然かもしれません。
そうした中で治外法権的に味噌(あるいは特定の食品)は体によいからたくさん摂ってOKと考えるのは筋が悪い選択であると言えるでしょう。味噌には健康に良い特徴があるかもしれないが、健康に害があるナトリウムの過剰摂取にもつながるので、注意しておこうと考えるのが適切です。
今回のように、健康によいという情報と、健康に悪いという情報が重なったときには、どちらが信頼性が高い情報なのか、どちらが効果が高い情報なのかを精査する必要が出てくるわけですね。
食塩濃度が高い食品はより一層注意が必要かもしれない


味噌に限らず「この食品は塩辛くてもOK」という質が高い研究はあまりありませんが、逆ならあります。
ナトリウムおよび塩分を多く含む食品の摂取とがんの関連を調べた研究によると、たらこや筋子、干物や塩だらなどの塩分濃度が高い食品は、胃がんの発生確率を上げるのです。イクラ丼好きなんだけどなあ……。
ちょっと不思議なのは、食塩摂取量が多いと胃がんになりやすいというわけではないということです。味噌や醤油などの調味料からの食塩摂取量と、胃がんの発症率には関係がありませんでした。



理屈で考えれば、醤油をかけすぎた刺し身と、塩漬けの魚で、病気になりやすさは変わらない気もするんですけどね……?
しかし、これらの疑問は個人で解決できるものではありません。未来の栄養学者に期待しておいてください。今日のところは、結局今日の我々はどうしたら良いかを考えましょう。
ナトリウムは控えめの方が良い、食塩濃度の高い食品は控えたほうが良い、両方の研究が同じ方向を向いているのであれば、食塩濃度の高い食品は控えめにしておくに越したことはなさそうです。
ナトリウムの過剰摂取を避ける方法はあるのか
対策1:ナトリウムが少ない調味料である酢、からし、代替塩を用いる
では、そもそもナトリウムを摂取しないで済む調味料はあるのでしょうか。
単純に酢とか、からしとか、ナトリウムを使わない調味量を使うことは悪くない選択です。一例として、塩だけで漬けた漬物と、甘酢漬けを比較すると、ナトリウムを半分程度に抑えることができます。
また、どうしても塩味を楽しみたい場合には、代替塩という選択肢もあります。WHOは低ナトリウム塩代替物の仕様に関するガイドラインを発表しています。これは食塩のナトリウムの半分をカリウムに置き換えた商品です。
味の素株式会社公式サイト「やさしお」商品ページ より引用
単純に考えれば、塩辛さは同じなのに、ナトリウムの含有量は半分なので、ナトリウム摂取量を抑えられます。



いい商品なんですが、若干風味が特徴的なんですよね。苦みといいますか、えぐみといいますか……。
スープや煮物であればあまり気にならないんですけど、塩を多く使うことが多い塩焼きのような料理こそ、この風味の影響を受けてしまうのが弱点とも言えます。
また、価格もネックでこちら実勢価格が100g400円超なので、普通の塩と比較するとかなり割高です。しかし、そもそも塩ってそんなに量使わないので、減塩醤油などと比較すると割高感も薄いかな、とも思います。
このようなデメリットはありつつも、使い所がある食品であることは間違いありませんのでご紹介いたしました。
対策2:カリウムを摂取してナトリウム過剰摂取による血圧上昇を和らげる


「スイカは腎臓に良い」 という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
結論を言えばそんなことは無いんですけど、カリウムをたくさん含んでおり、1回に食べる量が多くてたっぷりとカリウムが摂れるから、血圧を下げる働きがあって腎臓を守れるよね、というイメージからできた言葉だと思っています。
特定の食べ物が高血圧を特別に防ぐという話ではないのですが、カリウムを多く含む食品をしっかりと食べることは、健康維持のためには有用です。
2025年度版の食事摂取基準においてはカリウムは食塩過剰摂取による血圧上昇作用に拮抗作用を持っていること、ナトリウム/カリウム比が小さいほど心疾患や全死亡率に良い影響を与えることが示されています。
では、どのくらいカリウムを摂るとよいのでしょうか。食事摂取基準から、目標量を現状を整理してみます。
こうしてみると、目標と比較して摂取量が少ないので、積極的にカリウムを摂取するのは高血圧を防ぐためにおすすめできる行動といえます。
令和5年の国民健康・栄養調査をみると、野菜、果物、肉、魚、乳製品などの食品からカリウムを多く摂取しています。野菜や果物を多めに食べるのはカリウムを取って高血圧を予防するためにもよい食習慣と言えます。
たまに海藻類がカリウム豊富だからおすすめという記事も見ます。
100gあたりのカリウム量はたしかに多いのですが、海苔100gというのは非常識な量です。おでんの昆布のようにある程度まとまった量をたべられるならともかく、少量の海藻を頑張って食べる意義は薄いでしょう。



100gって、板のり30枚分以上ですよ? 食えるもんなら食ってみろって位の量です。
また、カリウムは別に万能薬ではありません。カリウム何gでナトリウム何gを排出するなんて研究はちょっと見たことがありません。少なくとも「ラーメンを汁まで飲んだあとにバナナ2本食べてカリウム摂ればノーカウント!」というほど都合が良いものではないでしょう。まずは減塩してください。
注意
上記の話は健康な成人を対象としています。腎機能や心機能が悪い場合には、カリウムの量を控えなければならない場合があります。
まとめ:ナトリウムの摂り過ぎに気をつけつつカリウムも摂ろう
- 何に入っているナトリウムでも過剰摂取のリスクはある
- 干物や塩蔵魚卵など塩辛い食事に含まれる食塩は胃がんの原因にもなる
- 酢、からし、代替塩を使うのは減塩に効果がある
- カリウムを適量摂取すると高血圧を予防する効果がある
というわけで、大枠として「食塩(ナトリウム)の摂り過ぎには気をつけよう」は揺らぎませんね。塩大好きな日本人が完全な減塩をするのはなかなか難しいですが、折に触れて減塩に取り組んでいただければと思います。調味料の使い方も解説しておりますので、こちらもどうぞ。





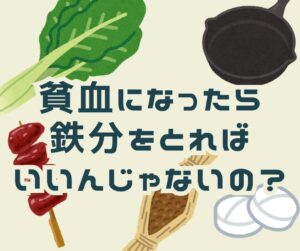

コメント